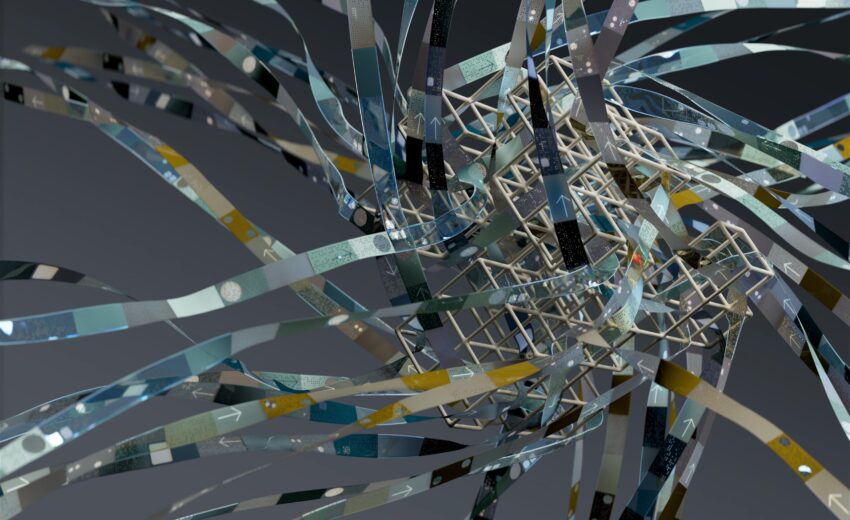新しいクライアントに、「なぜこの仕事をしているのですか」と聞かれる機会がありました。
2000年代初頭のユーザビリティという領域への接触が今の仕事の入り口だった、ではあるのですが、もう少し遡ると、大学院時代に触れていた知が、私の関心や世界の見方に影響を与えている思いあたり、少し文章にしてみます。
当時読んでいたのは、カルチュラル・スタディーズ周辺の議論です。
ロラン・バルトの神話作用や、スチュアート・ホールのエンコーディング/デコーディング理論。
ロラン・バルトが語った、「自然なもの」「当然のもの」として流通している「意味」が実は誰かの意図・意思で構築されている、という視点は私にはよい意味でショックを与えました。
また、送り手が込めた「意味」は、そのまま受け手に届くわけではないという、スチュアート・ホールの提示は、意味が形成されていくなかでも複雑な相互作用があることを教えてくれました。
こうして振り返ると、あの頃から一貫して「見えない力の作用」に面白さを感じていたのだと思います。
誰かが、何かしらの意図をもって環境を作っている。
それはいつしか当然化・自然化していく性質がある。
ただし常に環境を作った人の意図通りに人は理解するわけではない。
そうした問いは、いま扱っているUXという領域ともつながっています。
いま校正の段階にある著書で、パノプティコンを扱っています。
(「見られている」という意識の植え付けが囚人の行動を変えていくという話です)

社会には、意識されなくても作動している装置があります。
評価制度やKPI、アルゴリズム、インターフェースもそうです。それらは露骨な強制ではなく、むしろ「当然」のものとして機能します。
見えない力が自然化・当然化し、人の行動を決めていくという現象は避けられない。
だからこそ、その作用ができるだけフェアであること。
歪みがあれば補正されること。
人を不自由に閉じ込める方向ではなく、少しでも自由や豊かさを感じられる方向に働くこと。
そうした願いのようなものが、自分のバックグラウンドにはあるのだと思います。
大学院時代に触れた理論は、いまでは少し古い知に見えるかもしれません。しかし、その問いは終わっていないと感じています。
ダークパターンが注目を集めたり、AIがいかに倫理に配慮した返答をするかというトピックがホットになったりしていますが、これまで紡がれてきた知が議論に厚みを持たせてくれているようにも感じます。
意味はどのように作られるのか。
誰の前提が「当然」になるのか。
そして、その設計はどの方向を向いているのか。
私はいま、UXという実務のなかで、あの頃と同じ問いを、別の形で扱っているのだと思います。