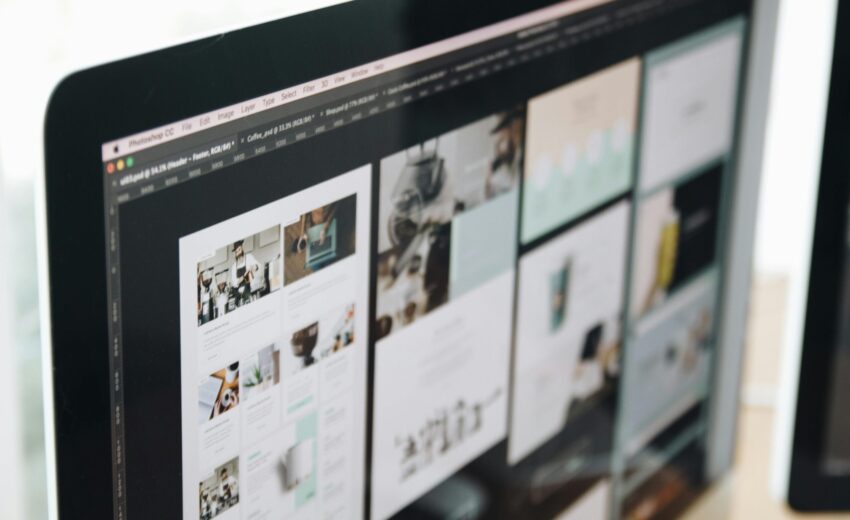かなり昔に読んだブログ記事だったと思うのですが、難しさの設計にも匙加減があって、
「何をやっても絶対に無理」
だと感じると、そのゲームは「クソゲー」になる。
逆に失敗しても、
「それが自分のせいだ」
と思えると、何度でもやりたくなる。
正確な言い回しは違っていたかもしれないが、そんな話でした。
クソゲーと良ゲーを分けるものは何か
当時は、ゲームの話として読んだ気がします。
レベルデザインの難しさ、といった文脈だったはずです。
けれど、この話はずっと頭のどこかに残り続けました。 あとから振り返ると、気に入っていたのはゲームという題材そのものではなく、「失敗の受け取り方が体験を決定づける」という視点だったのだと思います。
ここで言われている「クソゲー」と「良ゲー」の差は、成功率や上達スピードの話ではありません。
失敗しない設計かではなくて、失敗したときに、何が起きたのかが分かるかどうか、そして次に何を試せばよいかが想像できるかどうか。
その一点にあるように思えます。
失敗が「理不尽」に変わるとき
何度挑戦しても、理由が分からないまま跳ね返される。 操作は間違っていないはずなのに、結果だけが悪い。 改善したつもりでも、何も変わらない。
こうした状態に置かれると、人は「下手だから負けた」とは思えなくなります。 代わりに浮かぶのは、「これは無理な設定なのではないか」「自分がどうこうする余地はないのではないか」という感覚です。
この瞬間、体験はゲームではなくなります。理不尽な装置に変わる。
ゲーム研究者のJesper Juulは、『The Art of Failure』のなかで、失敗はゲームの本質であり、避けるべきものではないと述べています。
重要なのは、人は「失敗したい」わけではない、という点です。人が求めているのは、失敗を引き受けられる構造であり、失敗を通じて自分の理解が更新されていく感覚なのだ、と。
失敗がただの拒絶として返ってくるとき、それは学習にならない。 だから体験は、途端に壊れてしまう。
失敗が学習に変わる体験
一方で、失敗してもなお続けたくなる体験があります。 それは必ずしも、やさしい体験ではありません。むしろ、何度も失敗する。
それでも続けられるのは、「今回はここを誤った気がする」「次は別の手を試してみよう」と、自分の中に修正の仮説が残るからです。
Raph Kosterは『A Theory of Fun』のなかで、楽しさとは学習が進む感覚だと述べています。 理解が進まない反復は苦痛になる。逆に言えば、失敗が理解の更新につながる限り、人はそれを苦痛とは感じにくい。
ここで起きているのは、失敗そのものの評価ではなく、学習が前に進んでいるという手応えなのだと思います。
設計されているのは、失敗ではなく習熟の段差
ここで少し言い換えるなら、良い体験で設計されているのは失敗そのものではなく、習熟の段差なのだと思います。
よい体験には、
・いま自分がどの段階にいるのか
・何がまだできていないのか
・できるようになると何が変わるのか
が、うっすらとでも見える構造があります。
だから失敗しても、それは「拒絶」ではなく「途中経過」として受け取れる。
失敗の科学、という控えめな仮説
狙って失敗を仕込む、というのは少し難度が高い設計のように思います。
(教え上手な格闘家の先生が、「負ける理由が自分でわかるくらいの習熟レベルに進んだら、一度コテンパンに負けさせる」という高度な設計をされていましたが、なかなか真似しにくいですね)
設計者ができるのは、せいぜい次のことくらいでしょう。
・何が起きたのかが分かる状態を保つこと
・原因が無限に広がらないようにすること
・やり直しが効く余地を残すこと
失敗を「自分のせいだと思えるかどうか」は、最終的には体験する側が引き受ける感覚です。設計する側からコントロールできるものではない。
それでも、長く使われる体験や、何度も触りたくなる体験を振り返ると、そこには共通して、失敗が学習に変換される条件が整っているように見えます。
即座に返ってくるフィードバック。
原因が一つに近い状況。
成功への距離感が失われていないこと。
「クソゲー」と呼ばれる体験があるとすれば、それは失敗が多いからではなく、失敗が何にも変換されないからなのだと思います。
良い体験とは、成功させ続けることではなく、やり直したくなる状態を保ち続けること。
あのとき読んだブログ記事は、きっとそんなことを言いたかったのではないかと、いまは思っています。