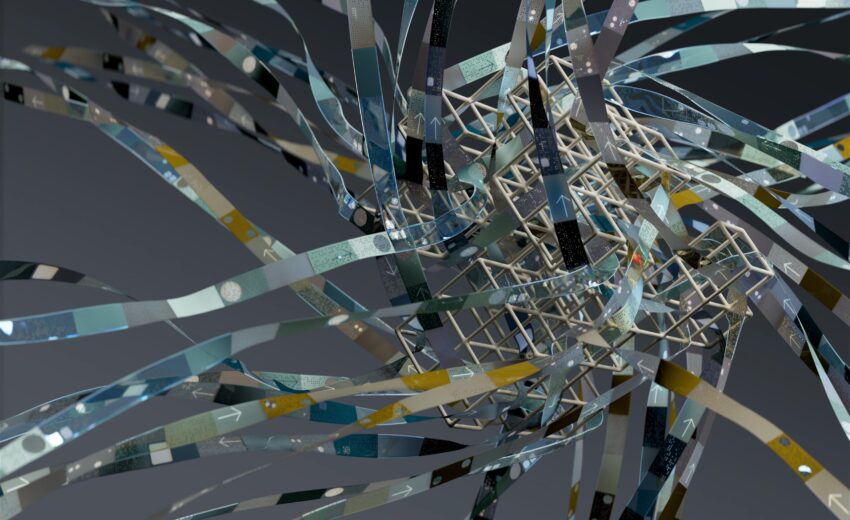何度か、同じような場面を見たことがあります。
会議の席で、経営者がふと視線を動かして、その場にいる一番若いメンバーに問いかけるのです。
「調査ではどうだったの?」
「実際、どんな反応だった?」
経験が豊富なわけでもない。
ただ、生活者に直接会い、話を聞き、その場に立ち会ってきた人。
少し不思議に見える光景かもしれません。
なぜ、わざわざ若いメンバーに聞くのか。
もっと整理された資料や、経験豊富な担当者の見解もあるはずなのに。
抽象に囲まれた意思決定
けれど、少し引いて考えてみると、合点がいくところもあります。
経営のもとには、抽象化された情報が日々集まってきます。
方針資料、戦略スライド、助言、レポート。
どれも間違ってはいないし、大きな方向感を捉えるには必要なものです。
ただ、そこにはどうしても欠けてしまうものがある。
現場の空気感や、言葉になる前の違和感、生活者の表情の揺れ。
つまり、リアリティです。
会社によっては、上に上がってくる報告が、きれいに丸められてしまうこともあります。
「大きな問題はありません」
「想定内です」
その言葉自体が嘘というわけではないけれど、現実のざらつきは削ぎ落とされてしまう。
ちゃんと考えたい経営者ほど、そうした抽象の層の下にあるものへの乾きがある。
だからこそ、経験の有無よりも、まだ加工されていない感覚を持つ人に、話を聞きたくなる。
若い現場のメンバーが、全体像や意思決定の背景に飢えるように、経営もまた、現場のリアリティのある声に飢えている。
そのあいだをつなぐもののひとつが、調査なのだと思います。
調査が持ち帰るもの
調査は、正解を出すための行為ではありません。
上手な結論を持ち帰ることが、必ずしも価値ではない。
むしろ、一次情報を、そのままの形で持ち帰ることに意味がある。
バイアスを極力除いて、聞いた言葉、見た反応、感じた違和感を、できるだけ歪めずに拾い上げる。
それがあるだけで、組織の中の議論は「戦えるもの」になります。
リアリティが持つ、静かな強さ
経験が浅くてもいい。
説明が拙くてもいい。
現実に触れてきたという事実そのものが、経験ある人の一般論や、統計的正しさが証明された話以上の力を持つことがある。
それは、どちらが正しいかという話ではありません。
蓄積された知識や抽象化された理解が無意味になるわけでもない。
ただ、リアリティのある感覚が組織に持ち込まれた瞬間、それまで当たり前だと思われていた前提が、静かに揺らぐことがある。
調査の価値は、その揺らぎを生み出せるところにある。
まだ言葉になりきらない現実を、結論にしてしまう前に差し出すこと。
肌感覚を養うといった意味があるからこそ、一次情報にふれることは重要。
移り気な現実に対応すべく、組織を変化させる材料になりえるのだと思います。